今回は株式会社の生い立ちを少し見ていきましょう。
株式会社とは、 「株」を発行して資金調達をし、
その代金で事業活動を行う会社のことです。
株式を買うことで誰でも出資者になれます。
この出資者のことを株主と言い、
事業が成功して利益が上がれば、
株数に応じて配当金や株主優待などを受け取ることができます。
経営者と出資者(株主)が別人でも構わないため、
ビジネス手腕のある人は、自己資金がなくても株式発行により資金を集めて事業ができるということです

時は大航海時代の17世紀
オランダやイギリス、フランスが作った東インド会社が世界で一番最初の株式会社だと言われています。
当時のヨーロッパでは肉を保存するための香辛料を求めて、
アフリカやアジアを目指す人たちが大勢いました。
しかし、当時の造船技術はまだまだ未熟だったため、
船旅には大きなリスクを伴っていました。
嵐などで船が沈んでしまえば、大損害です。
それまでは、船を買うのも、腕のいい船長を雇うのも、
船員を集めるのもすべて個人の資金で賄っていました。
見事香辛料を持ち帰って来れれば大儲けです。
しかし、失敗すれば場合によっては人生をだめにしてしまうほどのダメージを負うことになります。

このリスクをどうにか抑えられないかと考えだされたのが、「株式会社」という仕組みです。
株式会社では、一人で資金を用意するのではなく、
みんなで出し合います。
もし香辛料を持ち帰れれば利益はみんなで山分けということになります。
万が一航海に失敗したとしても、自分で出資したお金を損するだけで済みます。
これはその後の人類史を書き換えたと言える様な大発明でした![]()
今でこそ、
「出資したお金が戻ってこないなんてとんでもない!」
と考えられている世の中ですが、
当時では「破産された場合にもある程度は救済される法律」なんて整っていませんでしたから、
商売をするだけでも大きなリスクがありました。
そうした時代において、
「失敗しても出したお金を失うだけ、成功すれば大儲け」
というシステムはまさに画期的だったのです。
現在存在している会社の大半が、この東インド会社と同じ仕組みです。
みんなでお金を出し合って船を造ることが、「会社をつくる事」、
船長を雇うことが「会社の経営陣を雇うこと」になり、
その雇われた船長が船員を集めることが「社員を採用すること」になっただけなのです。
今までは株式会社を設立するためには1000万円の資金が必要でしたが、
2006年からは1円からでも作れるようになりました。
事業のアイデアを持っていれば、誰でも株式会社を作れるのです


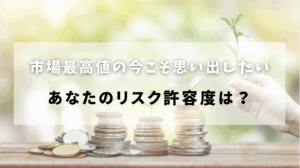



コメント